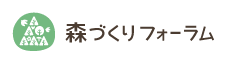『森の記憶を共有する』

10年くらい前、NHKの番組で対談をしていたとき、作家の高田宏さんが「森の前には必ず里の景色がある」というような話をされた。森と里とは一体になって、ひとつの景色をつくっている、という意味である。ところがその里の景色が目に入らず、森だけをみている「森の理論」や「森の思想」が多すぎて、それでは森のことは理解できないはずだ、と高田さんは言っていたのである。
私はいまでも、自分はもともとは釣り人だと自負している。子供の頃から釣りを通して川と関わってきた。そうして川の変化のなかに、日本の戦後社会の移り変わりや森の変遷を感じてきた。川は自然の世界を流れ、同時に人の世界を流れてきた。
森も同じである。森は自然の世界に展開し、人の世界に展開する。だから森の前には、その森と関わってきた里の景色が広がっている。
初めてナタやノコギリを腰に下げて山に入ったのは、25年ほど前のことだった。いまでは1年の半分を暮らす村になっている、群馬県上野村で、村人の畑の手伝いに森に入った。それはキューリやインゲンといったツル性の作物の支柱用の木を伐ってくるためで、直径2〜3cmの細い木を200〜300本、山から伐ってきた。
「柔らかい木を支柱(村ではこの支柱のことを「手」という)として伸びたインゲンなどには、柔らかい実がなり、固い木の手だと固い実になる」と、一緒に山に入った村人が言ったのを覚えている。本当にそうなのかどうかは、いまでもよくわからないのだけれど、支柱用の木の選択にも、村には村の記憶があるのである。「最近は細い木がなくなって困っている」ともその村人は言った。薪が生活のなかで使われていた頃には、萌芽更新してきた細い木がたくさんあった。畑や生活のなかで主に使われるのは、そういう木だ。ところが林業用の森が増え、木が太いものばかりになって、細い木がなくなってきた。
そんな話を聞きながら、木を伐りに行ったのが山に道具をもって入った最初だったから、私はいまでも畑から森をみることが多い。つまり、里の景色から森をみている。
森林や林業の問題に深入りしはじめた頃、私は、農業や村の暮らしとの関係で森のことを話すときの村人の柔和な表情と、林業問題を語るときの厳しい表情との違いが不思議だった。おそらくそれは、記憶の違いからきているのだろう。前者は何千年も、おそらくは人類の誕生以来つづいてきた森と人との関係である。だから村に暮らす人の体の奥深くに根付いている記憶とともにある。
ところが林業は、いわゆる先進的林業地を除けば、多くの村では明治以降、あるいは戦後の森と人との関係といってもよいのだから、新しい記憶、まだなじみきっていない記憶でしかないのである。市場経済のなかで闘っているという水準を越えていない。その結果、それについて話をするときには、経済人のような厳しい表情にもなる。
もちろん私は、だから林業は必要ないとは思っていないけれど、林業の前に、農業や暮らしとの関係を通してつくられた森の記憶がある、ということはみておかなければいけないと思う。その記憶の上に林業の記憶が重なりはじめ、村人はいまでもそのふたつの記憶の不調和に戸惑っているのだから。
「森とともに暮らす」とは、森と里とが一体化した景色のなかに何が隠されているのかを、感じながら暮らすことであろう。森だけが対象なのではない。たとえ都市のなかで暮らしていても、森と里とが一体となった景色と、そこに蓄積されている記憶を共有しながら、森と人との関係が永遠であるためには、自分たちはどうしたらよいのかを考え、行動していく。
「森づくりフォーラム」が、そんな人々のネットワークになることを私は期待している。
===============================================
写真:石井 春花(森づくりフォーラム)
※本記事は、NPO法人森づくりフォーラム 機関紙に掲載されたものです。
(2004年発行 No.100号に掲載)
===============================================