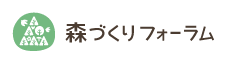川の話をしようとすると、どうしても昔話になってしまう。かつては素晴しい淵があり、瀬があった。その川のなかを山女(やまめ)や岩魚(いわな)が泳ぎ、森が川面に影を落していた。川風が川を伝い、鳥たちがその風に乗って飛んでいた。源流の川は、太古の昔からの永遠の営みを伝えつづけていた。
それはわずか30~40年前には、どこにでもあった、ありふれた景色だったのに、いまでは日本の昔話である。
上野村を流れる利根川の支流、神流川(かんながわ)でもおなじである。はじめてこの川に釣りに来た30年と少し前には、流れのなかに足を踏み入れるときは、カジカを踏まないように注意しなければならなかった。川底の石の間には、ハゼに似たカジカがいくらでもいた。源流部を包む国有林は原生的な森の面影を残していて、この深い森の底を神流川は流れていた。
ところが、今日の上野村の国有林は、かつて薪炭林であった村の国有林よりも弱々しい。大木はほぼ切りつくされ、ケヤキ、シオジ、トチ、・・・・、すべての大木は思い出のなかにしか存在しない。そして、森が切られていくにしたがって、川は土砂に埋まり、かつての神流川も記憶の底に沈んだ。
もっとも、その理由は、森の伐採だけにあったとは言えない。森の伐採と時期を同じくしてすすめられた林道工事や、治山、砂防ダムの建設の方が、川に大きな傷手を与えている。一般論としては、森林管理に林道は必要だとしても、林道の開削によって、山腹崩壊や土砂流出がつづくルートに、ずさんな林道を建設すれば、山と川を傷めるばかりである。治山、砂防ダムはそれ以上に悪い。常習的に山腹崩壊がおきているような例外的な谷を除けば、ほとんどの治山、砂防ダムは、川を破壊するために造られているようなものである。
神流川も、他の日本の川と同じように、このわずか30~40年の間に、古えの姿を失った。村人は現実の川を嘆き、記憶のなかの神流川を語るときにだけ、川の美しさを語り合うようになった。
かつては、夏になると、村の子どもたちは「石拾い」をして遊んだ。深い淵に、めずらしい色をした石をひとつ投げ込む。同時に子どもたちが川に飛び込み、その石を拾うのである。ところが、めったに拾えるものではなかった。淵の底は、村の子どもでも容易に到達できないほど深かった。
私が釣りに通うようになった頃には、まだ川底のみえない淵がいくつもあった。石を投げると、ユラユラと沈んでいって見えなくなる。
そんな淵の横の岩の上に座って時間をつぶしていると、ときどき大きな山女をみることがあった。一瞬、鯉だと錯覚したこともある。私はあわてて竿を延ばし、しかしこういう山女は釣れたことがない。面白いのは、こんな主のような山女をみると、釣ろうとして竿を出しているのに、気持ちのなかでは、私の延ばした餌をその山女が食べないことを願っていることだ。なぜなら、神秘ささえ漂わせる川の主は、人間より偉大であるべきなのだから。
こういう大山女のことは、村人も知っていて、あの淵には一匹いるというように話にのぼる。どんなに工夫をしても、誰も釣ることができず、そして誰もが釣れなかったことにホッとして帰ってくる。
この釣りをめぐる村の世界も、いまでは記憶のなかにしか存在しない。
2002.04.05 森づくりフォーラム会報79号寄稿