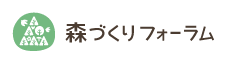『日本の社会』

日本の人々は、伝統的には、自分たちの社会は自然と生者と死者によってつくられている
と考えていた。生きている人だけが構成メンバーだと考えてきたヨーロッパと違って、
自然も死者もこの社会の構成メンバーだった。
ただし、この考え方には、少しだけ注釈をつけておく必要があるのかもしれない。
自然も社会の構成メンバーだという言い方をすると、日本では、自然と人間は同格だったととらえられるかもしれない。しかしそれは近代的なとらえ方で、伝統的な発想では、
自然との関係が自分たちの社会をつくっているということである。
どちらが上だとか、同格だというようなことはどうでもいい。
生者も同じことで、人間同士の関係がこの社会をつくっている。
死者との関係も同じで、近代的な発想だと死者も社会の構成メンバーだといえば、
死者の魂=霊は、本当に存在するのかどうかがまず問われることになる。
だが日本の伝統的な発想はそういうものではない。
死者とも関係を結びながら私たちは生きていて、
死者との関係もまたこの社会をつくっているこということである。
私たちの社会は自然との関係をとおしてつくられ、人間同士の、
そして死者という先輩たちとの関係をとおしてつくられている。
だからこの社会は、自然と生者と死者の社会だと考えてきたのが、
日本の伝統的な発想だった。
この感覚はいまでも案外残っていて、たとえば親しい人が亡くなったりすると
終わりになったという感覚よりも、その人との関係はいまもつづいていると
感じる人たちの方が多い。
昔は「そんなことをしたらご先祖様に申し訳が立たない」というような言い方が
あったけれど、死者との関係もまた自分たちの社会をつくっていたのである。
ここにあったのは、関係こそが本質をつくっているという考え方だった。
家族との関係が家族をつくり、地域との関係が地域をつくる。
つくりだしていく力は、すべて「関係」にある。
だから関係が成立するなら、その相手もまた存在する。
相手がいるから関係がつくりだされるのではなく、
関係がつくられているから相手が存在するのである。
いまではお盆だけになってしまったけれど、昔は正月も祖先が帰ってくる日だった。
神様を迎えるためにしめ縄を飾り、しめ縄の内側を神域とした。
先祖が戻り、自然も人間も死者も新年を迎えて一緒に歳をとった。
すべてが関係とともに存在しているのだから、すべてのものが歳を重ねるのである。
私の新年は、毎年上野村で迎える。年末には恒例の餅つきがおこなわれ、二日間で百臼を
超える餅がつかれる。集まってきた人たちも、集落の人たちも、その餅を用いて正月を迎える。
村の正月は寒い。夜はマイナス十度を超えることがあるから、すべてが凍りついているかのような世界だ。
雲のない日は星が空を埋めている。ときどき雪が舞っている。落ち葉の乾いた音がする。
そして私もまた、みなと一緒に歳を重ねたことに安堵している。
社会をどのようなものとしてとらえるかは、正しい答えがあるわけではない。
なぜなら、社会はある考えによってつくられたものではなく、自然に形成されたもの、
気がついたら存在していたものだからである。社会とは何かは、自然に形成されたものをどうとらえるかにすぎない。
だから欧米流の社会観があってもかまわないし、伝統的な日本の社会観があってもよい。
ただし、社会をどうとらえるのかによって、人々の精神世界や行動のし方は変わっていく。日本では、自分たちは関係的世界のなかで生きているという精神が生まれ、関係を大事にする行動や倫理観が生まれた。
とすると、森はどうあるべきなのかという発想も、欧米流の発想なのだということにある。出発点で、森を独立したものとしてとらえているからである。
日本の伝統的な考え方に従うのなら、森との関係の中で私たちは暮らしているということになる。この関係のなかに、森が存在し、私たちの営みが存在しているのだと。
課題は森自体ではなく、森との関係のあり方である。
上野村では、冬の森とともに正月を迎える。そして今年も、無事な関係がつづくことを祈る。無事な関係が森をつくり、村をつくっているのだという発想が、この村ではまだ生きている。
===============================================
日本の森を守るため、森づくりフォーラムへのご支援をよろしくお願いいたします。
https://www.moridukuri.jp/member/donation.html
※本記事は、「山林」(大日本山林会 発行)にて連載中のコラム
「山里紀行」より第308回『日本の社会』より引用しています。
(2017年1月発行号掲載)
★ 大日本山林会 会誌「山林」についてはこちら
===============================================