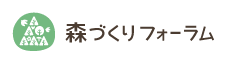『森の価値を最大化する営みをめざして』(後編)
※本記事は、2019年6月15日(土)に開催された「森林と市民を結ぶ全国の集い in 掛川・静岡」
における内山 節の基調講演の文字起こし記録となります。
前編はこちら
実際に森とともにある社会というのを考えていくと、よく受ける質問は
「群馬県の上野村はいいでしょう。目の前が森だし、むしろ村の面積の96%が森林ですし。けれども東京とか難波とかに住んでいる人間からすれば森は遠いし、近くにある自然はちょっとした公園くらいしかない。そういう人間が森とともに暮らすにはどうしたらいいのか」というものです。
そういった感覚というのは、生きていく人間だけで社会を考えるようになった時代の産物かなという気がしています。
例えば最近外国人旅行者に大変人気のある東京のスポットとして、浅草の浅草寺周辺があります。僕も東京にいるときに住んでいる家から、浅草寺のあたりを抜けたその先に行くことがよくあります。そうすると何曜日に通ろうとも、道は外国人旅行者だらけという感じです。
浅草寺というお寺は雷門の方、正門から先は江戸時代にすでに都市化していたという場所ですが、裏門の裏側にあたる部分は農村地域であったわけです。あのあたりの主要な農産物は小松菜が多かったんですが、江戸の市民に新鮮なまま野菜を届ける、そういう場所としての農村があった。そこに水利施設はそんなにありませんので、雨が降らないと作物が影響を受けるわけです。
そうした状況の中、昔の浅草寺の主たる役割として雨乞いがあったわけです。雨が降らない時期に雨乞いの儀式をする。その時に浅草寺はどういうやり方をしていたかといいますと、埼玉県は秩父の方に武甲山という山があるんですが、そこに行って湧き水をもらって帰ってきて、それを使って浅草寺で雨乞いをするということを昔はやっていました。それで雨が降ったかどうかは知りませんけども。
浅草寺は横に隅田川が流れていますが、隅田川は荒川の支流なので、荒川水系が流れていると考えればいい。荒川の上流に向かってさかのぼると、秩父に到達します。ですから自分たちの川の源流があって、その森から湧き水が出ている。そういう世界が実は自分たちの農村世界を守っている。雨が降らないと困るので源流の水をもらってきて、それをつかって神様かなんかに雨を降らせてもらおう、ということだろうと思います。
つまり昔の人たちというのは、はるか彼方にある世界と自分たちが結ばれていて、そういう世界に支えられて生きているということを、普通に知っていた。
東京には青梅という奥多摩の入り口みたいなところに御岳山という山があります。御岳山は山岳信仰における東京の中心の一つです。そこの山岳信仰の行者の人たちは、多摩地域の農民が多かった。御岳山の方にいくと多摩川源流になりますので、多摩川源流の世界、そこには川があったり森があったりするわけですけども、その世界とつながって支え合いながら、自分たちの多摩地域の農村世界がある。それをよく理解していたから、山岳信仰の行者さんたちは多摩地域と関わっていた。
つまりかつての人たちというのは、目の前にある自然だけではなくて、われわれの生きている世界というのが大きく自然に支えられ、森に支えられ、その結果として川に支えられていることを非常によく知っていた。
目の前にある自然としては、多摩丘陵地帯の農民からすれば、その地域にかつて雑木林がたくさんありました。それを全部壊して多摩ニュータウンをつくったということでもあるんですが、かつて里山的な森はたくさんあった。
そうすると片方では里山的な森が自分たちの生活を支えていることを感じながらも、もう一方においては、御岳山のような多摩川源流を形成しているような奥山的な世界が、また自分たちを支えている、という捉え方。そういう意味では、農村も都市も漁村も、あるいは大地や川や海やすべてのものが、森とともに展開しているということを、機能を超えて感じとっていた、という気がします。
機能を超えてなぜ感じとっていたのかといえば、そういう関係がわれわれを支えているということを何となく感じていた。奥の方の森が私たちを支えているという、そういう関係を感じてといった。
多摩丘陵地域でいえば、目の前に展開する里山的な森である雑木林が私たちを支えている、それも一つの関係。浅草寺のような都市と農村の支えのようなお寺で、何かあると源流の水をもらってきたりすることも、そういう関係を感じながら生きていることであるわけです。
私たちにとってピンチになってきているのは、その関係を感じとる力が残念ながら弱まってしまったということです。だから目の前に森がないと、森がないのにどうしたらいいの、という話になってしまう。だけど、もともとの日本の人たちの感じ方はそうではなくて、目の前に見えているものを利用するけれども、実は見えていないような世界、遠くの世界が我々を支えているということを感じていた。
実際、江戸時代の人々からすればやっぱり森は遠くにあったんですね。江戸時代の江戸の広さは、今の山手線の内側から半分くらいと思えばいいかなと。日本橋の方が山手線からはみ出ますけども、広さはそんなものかというところです。
江戸の町ができたときにどうしても木材が要りますので、木材ができるだけ近くにあるといい。重い木材を運ばなくていい、できたら近くがありがたいということだったんですね。
最初に形成された江戸の林業地帯は、新宿の四ツ谷林です。つまり四ツ谷を森にすることが可能だったということですね。ただそのうち無理になりまして、今度は杉並のあたりに移って、杉並だけれども四ツ谷林業という名前だけは残った。
今日はこの後パネルディスカッションで東京農業大学の宮林先生がお見えになっていますけれども、東京農業大学が初めにできた都市は青山ですから、原宿のあたりです。
東京農業大学も古い大学で、明治の初期からある大学ですけれども、農業大学を青山につくる場所があった。そのうち手狭になって世田谷に引っ越してきたという、まあそういう歴史もあります。
ですから江戸の町はそれくらいの広さの中にあった。ただ、歩きながら移動する生活からするには十分広かったので、当時の人々から見れば秩父の方、秩父地方には観音霊場巡り、遊びに行く観光地、みたいな形にはなりますが。それでも江戸時代で秩父に行けるのは生涯に一遍かぐらいの話だったりする。秩父まで歩いていくのは大変ですから、ほとんどの人たちは秩父源流なんて見たことが無い。
そういう場所なのに、遠くの山々に私たちは支えられながら生きている。この生きる世界をつくっている。その生きる世界は自然と生者と死者による社会で、この生きる世界をつくっているということを感じ取っていたんだという気がしています。
一つはそういうものを回復しながら、都市の人たちも含めて、私たちは森とともに暮らしているとことを、どう再認識していくか。そういうことが進んでいくことによって、森林を所有している人たちにとって、森を持っていること自体が誇りになっていく、そういうような価値の発見とか、そういったこともこれから少しずつ進めていきたいという風に思っています。とともに、森の持っている価値を最大にするにはどうしたら良いか。この場合、価値というのは経済的な価値だけではない。
昨年、秋田市で林業をやっている佐藤清太郎さんがみどりの文化賞を受賞されました。僕は佐藤さんとは結構昔から親しくしていただいています。昔で言えば地元の資産家でもあるし地元の第一林業家でもあるという方です。
佐藤さんはなかなかいろんなアイデアを出す人でもあって、今から30年ぐらい前かと思うんですけれども、日本海を通過した大きな台風がありました。その台風は、佐藤さんの森の一番価値が高い木をなぎ倒した。昔からの林業家ですから、やっぱり山の中には一部とても年齢の高い良い杉があって、なぜかその林がなぎ倒されてしまった。
ですから大変なダメージを受けたということではあるんですけれども、その直後にお伺いしたらば、全然萎垂れていなくて、「むしろこれは林業のやり方を変えるいいチャンスかもしれない!」とおっしゃっていました。
その時に彼が始めたのは天然林、まあ雑木林ですけれども、その中に3本の杉の木を三角形に植えるというものでした。それを点々と雑木林の中に植えていく。それが上手くいい木になるかどうかを楽しみながらやっているという感じでした。
それから20年ぐらい経って行ったら、それは実に上手くいっていた。周りに雑木林があて、ともかく杉が早く頭を抜くように植えたところ、まっすぐスーッと3本並んで、立ち上がっている。
はじめその3本というのは、そのうち育ちがいいものを1本残して、2本は間伐するというつもりだったんですけれども、これはもしかしたら間伐しなくてもいいかもしれない。そうすると100年くらい経って下の雑木林がつながって、杉が3本上に立っているような感じになるんだけど、このままも面白いかなぁ、とそんなことも楽しみながらやっていました。
彼は本当にいろんなことを考える人で、地域社会に高齢者が多くなったんで森の入り口に、いわば高齢者施設のようなものをつくって、それで、高齢者が施設に入って何にも仕事ができないっていうのはますますよくないから、高齢者に山の作業をしてもらおう、だけど足腰が悪くなるわけにいかないですから、普通の山の作業だと大変です。
彼が考えたのは杉の細い丸太を取る場所をつくって、その下にミョウガを植えた。ミョウガはギュウギュウに植わっているから、草が生えてこないので草刈の手間が掛からない。それで、高齢者でも多少元気な人は細い丸太を伐って出荷するという作業もしてもらって、足腰が悪い人たちはミョウガを採ってもらう。そういうのでいこう、と。
残念ながらそれは実現しませんでしたが、その杉林とミョウガ林っていうのはつくりましたので、なかなか変わったことをしています。
次にその彼がやっていたのは地域の幼稚園児、秋田市内とはいえ、そこは秋田市の外れみたいなところですので、秋田市内の幼稚園と提携して、幼稚園児に自分の森に来てもらう。今でいう「森のようちえん」なんですけれども、それを非常に古くからやっている。
そういうことをしながら彼は自分の森の価値を高めていった。その中でお金になる価値という点では、その後の木材価格の低迷を考えれば、良い木が残っていたとしても別に増えなかったという気がします。
まだ彼は何百ヘクタールと森林を持っておりますので、他の山では普通に丸太の出荷も致しますけれども、その経済的な収益をもたらす価値だけでなく、そうやって地域の人たちが森を使って、上手くはいかなかったけど高齢者の世界もできるし、それで子供たちが森で遊ぶことで地域の幼稚園の在り方も変わっていく。そういう中に自分の森の新しい価値を発見する。そういうことをやっていた人でもあった。基本は林業家ですけれども、彼は森の価値を再発見したんだなという感じがします。
一方、私のいる上野村ですが、上野村は人口1200人くらいの村で、しかもすごい山の奥です。ですから古い共同体的な雰囲気が非常に色濃く残っています。あえて僕はそれに惹かれていったという感じもあります。そのためにもはや個人個人で森を守っていくっていうのがちょっとピンチになってきたというときに、むしろ村の森として森を守るという方向にいった。
だから森は個人が誰かの所有番地はあるけれども、森は個人のものである以上に、村という共同体の共有財産だということです。その共有財産をうまく管理運営していくというのは共同体の役割。
それで村はいろんなことを考えて、森の中で間伐をしたりするような作業をする人たちもいるし、上野村には森林組合がありまして、その森林組合が製材工場を持っておりますので、そこで製材をする。また村には木工職人っていう人たちが20人~30人くらいいて、小さな茶托みたいなものから大型の家具まで、職人一人一人が得意な分野があるので、それでいろんな木工品をつくる。
さらには森を手入れすることを目的とした伐採もします。幹から切っているわけじゃないんです。山の木を伐っても、上野村は特に紅葉樹が多いこともあって、利用できる材は大体40%くらいで、60%くらいは伐っても利用できない木です。それは山の中で放置すると、山が急傾斜なので災害時に危ないということがあって、うちの村は昔から伐ったら全部運び出すというやり方をとってきた。
伐ったうちの6割が運び出しても使えないので、その6割を使って木質性のペレットをつくって、そのペレットを使って冬場の家とか役場とか色んな施設の暖房装置のエネルギーとして使っています。あとは、農業用ハウス、温泉の過熱とか過熱ボイラー用の燃料にも使っています。実際にはペレットの内60%は発電に使っています。
もう一つには山の広葉樹、うちはコナラ、ミズナラですけども、ナラ系の木が伐採されてきたときには、それをおがくずにして、そこからキノコの菌床をつくって、キノコをつくります。キノコが生えなくなった菌床は、それを原料にペレットをつくるという循環の仕組みをつくり上げている。うちの村はキノコの出荷量が4億円くらいになっています。1200人の村で4億円ですから、これは一大産業なので大事なんです。
そのように一人一人の森ではあるけれども共同体の森と考えて、その中では山中で作業する人もいるし、製材している人もいるし、木工をやっている人もいるし、あるいはペレットにしている人もいるし、本職ではキノコ栽培の方で動いている人たちもいるし、とそういう全体の中で森を守る。で同時にそうやってきれいな森をつくることで、それが村の観光資源になってもいるということでもあります。
先ほどの佐藤清太郎さんは、自分のいろんな企画力と実行力によって森に新しい価値をつくっていく。今度は逆にうちの村になると、そういう所有者が自分でつくるという感じよりも共同体としてつくりましょう、共同体として森の価値を再創造しましょうという方向にした。それは1200人ぐらいの村であり、そして役場の職員さんは村人の全員の顔と名前が分かるくらいの規模の村ですから、そういうことが可能です。やり方は、いろいろあるんだろうという気がいたします。
地域の違いもあるし、所有者たちの指揮の違いもあるし、考え方の違いもあるし、だからいろんな多様性があっていいんだけれど、私たちはどうにか新しく所有者にとっての価値というものを再統合しなければいけないところにきた。
冒頭申し上げたように、かつて森林は生活林として価値があった。資産林としても価値があった。そして収益林としても価値があった。このことに依存して森林を守ろうとすると、そのいずれもが崩壊しています。崩壊はちょっと言い過ぎかもしれないけど、実は国内の森林所有者の大半が小規模の所有者で、その森林所有者たちにとっては崩壊しているんです。それでもなおまだ収益が出せるのは、日本の中でもほんのわずかの大林業家にすぎないということであります。
上野村のように、みんなが少しずつ森を持っているようなそういう森林からすれば、もう収益林として終わっているし、資産でも無い。だけど持ち続ける誇りみたいなものをつくっていけるような価値の創造をしなければいけない。今度はその価値を見つけ出してきたならば、そういうものを支えていくような社会的な仕組みをつくっていかなければいけない。
そこで今回の主催地で、実行委員となっている「NPO法人 時ノ寿の森クラブ」もそうだと思いますけど、やはりそれは新しく森に価値をつくる仕組みといってもいいわけですね。
その仕組みをつくりながら、私たちはどうやって所有者にとっても、一見関係ないと思われるような外の人たちにとってみても、愛おしく感じる森であり、自分たちと共にあると感じられる森でもあり、あとは自分たちの命の世界の中に森があると感じられる森、そういう世界をこれからどうつくっていくのか。つまり、機能だけで森を見てはいけない、ということをこれからやっていきたいなと思っています。
そういう点でいうと、今は伝統回帰の時代と捉えてもよい。昔の人たちの森との結ばれ方から、もう一度学びなおすという意味で伝統回帰です。伝統回帰とは、昔の形に戻すことじゃないんですね。昔の考え方から学びなおすことです。
例えば私の村では木質系のペレットをつくって、それで発電もしているし、いろんな暖房その他にも使っていると先ほど申し上げました。そうすると「山奥の村なのにずいぶん新しいことに取り組んでいますね。」とよく言われますが、確かに現象としては新しいことに取り組んでいます。
だけど考え方は昔に戻ろうとしているんです。つまり地域エネルギーで生きた時代に戻ると。それからその地域エネルギーの柱が薪だった時代に戻ると。ただ、薪が使える人は薪にいけばいいんですけど、全員が薪に戻りなさいっていうと、やっぱり高齢者も多いですし、なかなかそう簡単にもいかないという現実がある。
そうすると、今の技術を使ってペレットにして非常に使いやすくしている仕組みがある。だから現象的にはペレットも生産し、それで発電までやることになりますから新しい試みになるんですけど、考え方としては昔の地域社会に、地域連携で暮らした時代に戻っている。しかも薪で暮らした時代に戻る。ただやり方は新しいです。つまりこれが伝統回帰です。
ですから、そういう点では昔のいろんな社会観を含めて学びなおしながら、それを活かした現代の仕組みをつくっていくということです。そんなこともこれからは大きな課題としながら、私たちは社会全体にとっても、地域社会にとっても、それから森林を所有している人間たちにとっても、森林の価値が最大化される、そのことを実現させる知恵。それがいま求められている時代なのではないかなと思っています。
というわけで、はじめに自分が普段考えているようなことをざっくばらんに問題提起として申し上げました。どうもご清聴ありがとうございました。(終わり)
===============================================
日本の森を守るため、森づくりフォーラムへのご支援をよろしくお願いいたします。
https://www.moridukuri.jp/member/donation.html
===============================================