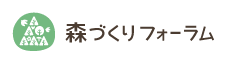『森の価値を最大化する営みをめざして』(前編)
※本記事は、2019年6月15日(土)に開催された「森林と市民を結ぶ全国の集い in 掛川・静岡」
における内山 節の基調講演の文字起こし記録(前編)となります。

ご紹介いただきました内山です。私は掛川市とは榛村純一前市長時代から付き合いが多くて、掛川市にはこれまでに2、30回は来ているのではないでしょうか。いろんな方々に大変お世話になっています。
私は50年近く前から、東京と群馬県の上野村という村を行ったり来たりという生活をしております。掛川市も市の面積の半分が森林というふうに先ほど伺いましたけれども、上野村は森林率が96%という村で、しかも村の中には歴史的に水源がないというところです。
上野村の主要産業は、昔は養蚕で、そのあと和紙の生産になりましたが、今はキノコの生産が1番大きいという、そんな感じです。村の人口は1200人ほどです。明治以降、一度も合併したことがなく、比較的、山村の中では元気な村で、何とかしていこうと村民みんなで結束して頑張っていこう、というような村に年間の半分ぐらいおります。
日本の中で森林ボランティア的な活動が始まりましたのは、今から半世紀くらい前のことだという気がいたします。最初のころは特に人工林の間伐の遅れがあったみたいで、各地で荒れた森林が目立ってきた。そういう中で市民の中でできることはないだろうかというようなところから、この森林ボランティア活動は始まった。
その活動が全国に広がる中で、今では大変に多様化してきています。森林の中で活動することも一つだし、それからまた森のあるところに行けば、必ず地域社会がありますから、その地域社会をどう守っていくのかとか、あるいはつくっていくのかとか、そういうこともあります。さらには森を守ったり地域を守ったりしていこうとすると、都市の人たちとの連携をどうつくっていくのか、とかいうこともあります。
最近では、教育的あるいは森林教育的に森林を活用するような活動がありますので、初めは本当に荒れた森林を目の前にして、何とかしようというところから始まったんですけれども、今では森を柱にして、この社会のいろんなことを考えていこう、あるいは活動していこうという活動に広がってきたような気がいたします。
そういうことで、森林ボランティア的な活動というものも、目標として森とともに暮らす社会をつくろう、森林の近くに住んでいる人たちもそうだけれども、森林からは遠くに住んでいる人たちも含めて、全体として森とともに暮らす社会とはどんな形になったらいいのだろうか、そんなことを目標にしながらいろんな活動が進んできたという気がいたします。
実は私、今回の「森林と市民を結ぶ全国の集い」の実行委員会に加わっている森づくりフォーラムというNPOの代表理事を結成以来から務めております。現実は名前だけの代表理事で、実際の活動はほとんど若いスタッフに任せっぱなしという形ですが。一応そういうことでもあります。
こうした森にかかわる活動について、これまでの森の歴史を見ながら考えていきますと、森には大雑把に3つの価値があるという気がいたします。まず1つは社会にとっての価値。たとえば二酸化炭素を固定化する機能、地球の温暖化を防止する機能。これは社会にというより世界にとって、といった方がいいかもしれません。そういう社会全体にとって非常に大きな価値があるということでございます。
それから2つ目は地域社会にとっての森の価値。それから3つ目には、所有者たちにとっての森の価値というのも、かつてはありました。残念ながら今日になりますと、その所有者としての森林の価値というのが極めて低くなってしまったというのが本当のところかという気がします。
かつて所有者にとって、森は生活の中でとても重要でした。まずは薪が重要ですし、またいろんな農作業をするときの道具の材料となる木、例えば鍬の柄とか。そういうものも森が提供しておりました。それからいろんな地域の行事でも、その材料を森が提供しておりました。ですから、いろんな意味で森は生活林としての役割があった。
それから森自体が大変重要な資産であったということもあります。森を多く持っている人は、地元では資産家と呼ばれてきました。そして森の所有権が移動する、昔の場合ですと借金の肩で移動するということがよくあった。
ということは、借金の肩にできるくらいの資産的価値があったといってもいいわけです。今は、森を担保にしてお金を借りようとしても金融機関が貸してくれるのかという、残念ながらそんな状況になっています。森林の所有面積にもよりますが、かつて森というものが、大なり小なり何らかの収益をもたらしてくれた。林業的な価値といってもいいのですけれども、そういう場所でもあったわけです。
私が上野村という村に初めて行ったのは1970年代に入ったぐらいです。そのときに村の高齢者の方によく言われたのは、1950年代の終わり近くぐらいまでは暇な時、朝そんなに急がないで朝ご飯を食べてからゆっくり山にのぼって、それで山の木を少し切って、それで午後にはそれを庭に降ろしてきて、それで薪をつくったそうです。薪ですからそれを販売した。大体1週間ぐらい薪をつくると、役場の職員のひと月分の給料になったそうです。
だからそのころは役場職員になるなんて、なんて馬鹿なことをしているんだと、地元の人たちは思ってきたということでした。しかし、そのうち薪は売れなくなってしまいまして、あのとき役場職員になっていればよかったなあと、そういったような逆転があったと村の高齢者によく聞きました。
ですから上野村では結構薪の出荷量も多かったし、そのころまでは炭の出荷量も大変多かった。つまり所有資産としてだけではなくて、薪も売れるし炭も売れるし、森はいろんな収益をもたらしてくれた。所有者にとってみると、生活林であり、資産林であり、収益林でもあった。それが所有者にとっての森の価値ということだったのだろうと思います。
ところが今日、生活林としての森の価値というのが著しく低下した。薪が無ければ生活できない、というような時代でもなくなってしまって、むしろ今、薪を使っている人たちは贅沢な生活をしているという感じの時代になりました。
また、よほど良い木を持っているような森なら別ですけれども、上野村の人たちが持っているような森ですと、資産的な価値はゼロといってもいいような状況になってしまいました。さらには林業的なものも含めて何らかの収益をもたらすかというと、それも苦しくなってしまった。
ということになりますと、所有者にとって森を持つということは、どういう価値があるのかということを、今の時代に合わせて新しく再発見しなければいけなくなっている、という気がします。
所有者にとって価値がなくなってきたときに、むしろ世の中としては、森が環境的な意味で非常に大きな役割をもっているとか、昨今では温暖化防止との関係で非常に重要な役割を果たしているとか、そういう形で新しい森の価値を提起していきたい。それは間違いではないんですけれども、所有者にとってそれが所有する価値になるかというと、残念ながら、ならないといってもいい気がする。
つまり自分の森を見ながら「この森は温暖化防止にいくらか役に立っている。」と考えている所有者はおりませんので、社会的な価値と所有者の所有的価値みたいなものを、どこで折り合いをつけたらいいのか、ということが問われる時代にもなってきた。
そうすると新しい形で、社会全体で森を支えていく、社会全体で支えていくための仕組みをつくることによって、所有者自身にも自分の森はどういう役割を果たしているんだと、だから森を持っているのはやっぱり良いことな気がする。それが分かるような社会をつくっていかなければならない。そういうことを目指しながら活動しているのは、今の全国のボランティア的な市民たち、という気がしております。
森の話にもう一度入る前に、私は、日本との比較地としてフランスを使ってきました。フランスには、ずいぶんよく参りました。上野村に行くようになったそもそものきっかけが、魚釣りがしたいということで、行ってみたら村の雰囲気がとっても良くって、住み着いてしまったという、そんな感じの人間ですので、フランスに行きましてもやっぱり魚釣りがしたいことがたまにあったりする。
そうするとフランスの農山村地域に行ってちょっと魚を釣る。釣れるかどうかは別として、ともかく川に行って糸を垂らせば気持ちがいいというような人間ですので、結果としてフランスの、特に農山村地域のいろんなところに行ってきました。それで、フランスの農山村地域に行きますと、とってもいい地域社会があったりする。それはもう本当にいいなあと思う場所がたくさんあります。
ただ、やはり日本とフランスは違いもあるなあという気はする。その違いの中の一つは、「社会」という言葉を使ったときに、社会は誰によってつくられているのかという考え方が違うということですね。これはフランスに限らず欧米社会全部そうですけども、社会をだれがつくっているのかというと「生きている人間たちがつくっている」というのが向こうの考え方でございます。
ところがそれに対して、日本の伝統的な考え方では、社会をつくっているのは生きている人間だけではない、「自然と人間がつくっている」となる。自然はこの社会の構成メンバーであるという、そういう考え方を持ってきた。それからその人間の中には、生きている人間だけではなくて死者も含めることが日本の社会の捉え方だった。正確にいうと、自然と生者と死者によってこの社会はできている、とする捉え方です。
この感覚は今でも残っていて、例えば誰かが亡くなったりしますと、特に身内の人間が亡くなったり、あるいはかなり親しい人が亡くなったりすると、亡くなったから消えてしまったと思っている人はめったにいなくって、ほとんどの人達は「姿は見えなくなった。姿は見えなくなったけれども今もこの社会を支えてくれているし、守ってくれているし、ひょっとしたら、とんでもないことをやろうとするとご先祖様がやってきて、戒めてくれるかもしれない。」というような感覚をもっている。
だから亡くなった人との関係というものをとっても大事にする。ですから家の中に仏壇があって、朝にはお茶を持っていくとか、なんかいいものを貰うととりあえず仏壇に持っていく。そんなことをするのがごく普通にある。つまりそれは亡くなった人たちは、消えてしまった人たちではなくて、姿は見えなくなったけど今のこの社会を支えている人という、むしろそういう捉え方をしている。日本の社会観というのは自然と生者と死者によってこの世界はできている、ということです。
実は自治という考え方も欧米と全然違います。欧米の場合には生きている人間によって社会ができていますから、そうすると、自治をするとは、生きている人間たちが集まってきて議論をして方針を決めて実行すればよい。もちろんこれを本当にやろうとすると結構大変なことで、みんなの意見を1つにすることは容易なことではありませんけれども、原理的には簡単です。生きている人間が集まって、自分たちのルールを決めて実行すればよい。ただそれだけのこと、ということになります。
ところが日本の場合にはややこしくなっちゃうのが、何かを決めるときに自然の意見を反映させなければいけないし、それから亡くなった先輩たちの意見も反映させなければいけない。ご先祖様の意見と自然の意見を入れて決めなければいけないので、生きている人間だけで勝手に決めるのは社会のルールづくりとしては正しくない。けれども集まって議論しようとしても、自然と亡くなった人たちは集まってきて発言してくれるわけではない。
そこで、祭りとか年中行事とかが重要になってくる。つまり祭りによって自然の神様を降ろしてきたり、あるいは年中行事によってそういう自然の神々とどこかで交わったり、あるいはいろんな行事の中で絶えずご先祖様と付き合う。
ちなみにご先祖様という言葉は、明治時代以前の日本では、自分の家のご先祖様だけを指す言葉ではなくて、地域社会をつくってくれた先輩たちはみんなご先祖様とされていました。それが明治になると「うちのご先祖様」だけに特化されてしてしまった。
柳田國男もいっていますけれども、ご先祖様が固有名詞で呼ばれるようになったのは最近のことで、昔は地域社会をつくってくれた先輩たちがみんなご先祖様だった。だからそこには太郎兵衛さんも次郎兵衛さんもいるけど、固有名詞ので呼ぶ人たちではなかった。それが「我が家のご先祖様」に特化されたから、うちのおじいさんの名前とかおばあさんの名前とかいうことになったりする。これは明治以降の変化だっていうふうに思っていただいてよいです。
ですから、元々の意味でのご先祖様たちのありがたさを絶えず感じることが必要なわけで、それは墓参りをしたりお盆をやったり、あるいは1年間で見るといろんな行事がありましたけども、そういうことをしながら、生きている人間が自分の意見だけで突っ走るようなことをしてはいけない。私たちが生きている背景には、自然があり、ご先祖様がいる。ということを絶えず再確認して、そのことを通して集まって議論をしなければいけなかった。
日本の場合には、祭りとか年中行事っていうのはイベントではなくて、むしろ自治の仕組みの一環であると考えたほうが良いと思います。実際、いま過疎化が進んでいるといわれていますが、人口が減っても元気な地域もあります。そういう地域で必ず共通しているのは、祭りとか年中行事がきちんと残っている。大昔のものから全て残っているわけじゃないですけれども、少なくとも主要なものはきちんと維持されている。そういう地域は人口が減っても依然として元気だなという一面をみました。
それに対して人口も減って、ある時ぐらいから昔やっていた年中行事や祭りとかが全部無くなってしまった地域をみると、残念ながらこの地域はこれから危ないなという、力のなさを感じるということでもあります。
森というものも、社会の外にある森ではなくて、実は森もこの社会の一員であって、ちゃんと発言権も持っている存在です。ただ発言はしてくれませんから、森の代わりに私たちがしなければいけないという、そういう風に考えなければいけないということになります。私は「森」という言葉を使ってきたんですけど、日本の伝統的な言葉の使い方から言うと「森」というよりはむしろ「山」といった方が良いです。日本では、山は必ずしも傾斜地のことではなくて、「森」のことを「山」と呼んできた。
僕は東京都の世田谷区の生まれで、世田谷区は小さい頃にどんどん住宅地になっていったところです。昔の、明治時代や大正時代の世田谷区は、農村農地の手前側でした。ここは江戸時代に江戸という大きな町ができたんで、江戸の町に野菜を届ける畑作地帯としてできあがっていった。ここはあまり水の便がいいところが少なかった。たまたま水のある場所はありますが、多くは台地状になっていて水があまり無い。ですから水源はほとんどない中で、畑作をやって生鮮野菜を江戸に届ける、というそんな場所になっていた。
一番困っていたのは肥料が足りないという問題でした。稲作すれば、稲藁で堆肥をつくることができますが、例えば小松菜の葉っぱの枯れた部分で堆肥をつくるのは、少しはできるかもしれませんけど、ほとんど畑の肥料としては無意味だというくらいしかできなかった。ですから、そういう状況でどうやって肥料を加工するかということで、世田谷や武蔵野といわれていた地域では、農村を開いていくときに農地面積とほぼ同じ面積の落葉広葉樹の雑木林をつくった。
世田谷はクヌギとかコナラとか、そういう木を植えることが多かった。その落ち葉を利用して堆肥をつくる。後は下に生えてくる草を刈って堆肥をつくった。だいたい畑と同じくらいの広さの雑木林が必要だったとされています。昔のそのあたりの景色は畑があって横に雑木林があって、という景色が広がっていました。
そういうことで、うちの方は傾斜地の山は無いんですが、農家の人たちは「明日は山に行く。」といっていたりした。山という名の雑木林に行くわけで、その雑木林は夏になると子供たちがカブトムシを取りに行くのに丁度いいような平地の森です。そんな風に日本では森のことを山と呼んだりした。
ではその山とは何だったのかというと、先ほど言ったように生活をする場所でもあった。武蔵野台地では、農業用としてとっても重要な役割を果たす場所でもあった。けれども山は、この場合少し傾斜のある方の山になってまいりますけども、亡くなった人たちの魂が帰る場所でもあったといいます。
群馬県に、今は中之条町に入っていると思いますけども、六合村(くにむら)という村がありまして、合併して無くなりましたが、六合村は群馬の人しか絶対に読めなくて、六つ合うと書いて六合(くに)と読みまして、草津温泉の近くの村です。
そこは養蚕地帯で、日常にとてもいい昔の養蚕文化が続いている。実はここで明治10年頃に大火がありまして、ほとんど燃えましら。そのころ養蚕をやっていた人たちは、懐具合がよくて、大火のあとでも立派な養蚕農家をみんな再建した。ということで今でも道路の向こう側に見事な古い町並みが残っていて、伝統的建造物群として保存されている。
これは文化庁の指定になりますが、保存するということになりかかったときに、そこの住民たちから文化庁の指定は不十分だという声があがりました。なぜかというと建物だけ保存するということだから。自分たちが保存したいのは建物ではなくて、村を保存したいんだと。村をこれからも守っていきたいんだということでした。
実際に伝統的建造物群というのは全国で100か所ほど指定されていますが、だんだんそこが一種の町並みテーマパークみたいになって、土産物屋が並んでいたり、民宿が続いていたりする感じになって、そこの地域社会で暮らしている人はすごい様変わりして、昔の暮らしは崩壊している。残念ながらそういう地域がいっぱいあるわけです。
ですから赤岩集落の人たちは、そういうことを繰り返したくない。自分たちは建物の保存だけじゃなくて村を保存したい、ということになりました。当時の六合村が村条例をつくり、さらに県がそれを後押しするような形をとって、国の指定からは漏れているけれども、村を守っていくためにはとても重要だと思われるものを保存対象にするということをした。
その時、村の人たちから最初にこれを保存しなければだめといわれたのが、裏山だった。裏山といっても普段薪を採ったりしている山で、立派な大木があるわけではなくて、むしろ雑木林というような感じのところですが、そこを保護しなければいけない。その理由は、あの裏山は死者の魂が帰るところだから、ということでした。
村というのは、自然と生者と死者が一緒になってつくっているのが村なのに、建物だけ保存というのはとんでもなくて、亡くなった人たちの魂が生活する場所、そこをちゃんと保障しないと村がなくなる。それが村人たちの声でした。いわゆる貴重な動植物がいるなんて話もない森ですけども、地域の村を守るという視点からいくとまずそれが保存対象になる。
その裏山の下の入り口あたりには、たくさんのお堂があります。小さなお堂ですけれども、阿弥陀堂があったり、神の堂があったり、地蔵堂があったり、観音さまがいたりしますが、住職さんがいるようなところではありません。そこの場所で仏に守られながら、死者の山に帰っていく。だから地蔵堂や阿弥陀堂も保存対象にしなければいけない。そういう場所にだいたい墓がつくってあります。
墓というのは、亡くなったあと魂がそこから抜けて山に行くということなので、そうすると死者の魂がいく山の下あたりに墓があって、それも保存対象となる。そういう感じで何もかもが保存対象ということになってくるんですけども、その時に、村というのは自然と生者と死者の村だということを、村中の人が自覚している村があるんだということに、僕はびっくりしました。
つまり、もともと山というのは生活のための場所でもあるし、死者の帰る場所でもあるし、そしてそれは真実の世界でもあるし、とそういうものでもあった。そういうことを通しながら、かつての人たちは山とか森につながっていた。だから決して機能だけでつながっていたわけではないということです。
もちろん機能としてもつながっている。かつては生活の中で薪がとても重要ですから、薪を供給する森というのはとても大事なものだった。これは機能的なつながりといってもいい。それだけではなくて、死者たちの世界、生きている人間の世界、自然の世界、その全体の中にわれわれの社会があるという捉え方の中で、私たちは森という、昔の言葉でいえば山ですが、それを大事にしてきた。機能を超えた山の価値というものを感じていたり、大事に思ったりして生きていた。そのことを最近振り返ったりしています。
(後編へ続く)※2019年8月27日頃に公開予定です。
===============================================
日本の森を守るため、森づくりフォーラムへのご支援をよろしくお願いいたします。
https://www.moridukuri.jp/member/donation.html
===============================================