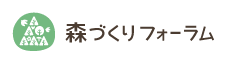生物多様性という言葉を聞くと、私たちは生物種の多様性をイメージする。そこから森林の領域では、間伐の遅れた人工林では下層植生が乏しくなり、生物種の少ない森が生まれる、といったことなどが連想されてくる。適切な森林管理が生物種の多様な森を生む、という視点である。
もちろんこのことも生物多様性の軸のひとつであることに変わりはない。だがそれだけが生物多様性ではないのである。
生物多様性と生物種の多様性は同じではない。たとえば犬は生物種としては一種である。しかし現実にはさまざまな種類の犬がいる。血統としての種類だけではなく、猟犬、盲導犬、介助犬等々として人間の近くで暮らしている。そのことは犬という生物種が保全されればよい、ということではないことを教えている。犬は人間との関わりにおいて、多様に存在しているのである。生物多様性とは、この関わりの多様性を保証していこうということである。
もちろん、生物と生物、生物と人間の関係の多様性を保証しようとすれば、生物種もまた多様でなければならない。その点では生物種の多様性は大事な要素である。しかし、生物種の多様性と生物多様性は同じではないし、むしろ生物多様性の一要素として生物種の多様性がある、と考えた方がいい。
○
かつての山村には多様な生物と人間の関係が存在していた。その関係は地域によって異なっていたが、どこの地域でも森林の第一の役割が燃料の確保であったことは間違いない。この薪を採る山は今日では「里山」として語られているが、そこは薪の採取だけに使われていたわけではなかった。水田が少ない地域では落ち葉や青草が肥料として用いられていたし、そこは山菜がよく出る場所のひとつでもあった。この薪山と畑の間には、帯状の草原があった。牛馬が飼われている間は、この傾斜地の草原と畦の草が牛馬の餌として用いられ、そこもまた山菜がよく育つ場所であった。
草原の下には田畑がつくられている。水田は今日では稲を栽培する場所のみになっているが、かつての水田は水路と一体となった水田漁労の場所でもあった。私もいまから45年ほど前に、農家の人とともに水田漁労をおこなったことがある。雨の後の捕りやすい時期におこなったのだが、1時間で背負子に半分ほどのドジョウやフナが捕れた。
薪山を上に上っていくと、山は次第に奥山の様相をみせていく。そこからの人と森の関わりは林業地であるかどうかなどによって異なってくるが、人々が茸や木の実を採り、狩猟をしてきたのはこの場所である。奥深い山では木地師が暮らしているところもあった。そして山の険しい部分は日本では信仰の場所とされることが多かった。
一昔前までは森と人間のあいだにも多様な関係があり、この関係のなかでさまざまな生物たちも暮らしてきたのである。
その頃は生物と人間の関係も複雑だった。たとえばイナゴは稲にとっては「害虫」であるが、それは村人たちの蛋白源として活用されてもいた。蛇が好きな人は少ないが、私の暮らす上野村では蛇神様が祀られている。かつて養蚕が主産業だったこの村では、繭を食べにくるネズミは天敵で、ネズミを捕ってくれる蛇は養蚕の守り神だったのである。群馬県にはいまでも蔵の入り口などにネズミ返しというものが取り付けられていて、ネズミが壁を上れない工夫をしているものがある。
山の動物も同じで、畑を荒らせば害獣になるが、それらは村に暮らす仲間としても人間と関わり、さらには冬には狩猟の対象になり、しかし人々の尊敬も受けながらときに神の使いとして扱われることもあった。しかもキツネやタヌキ、オコジョ、イタチ、ムジナなどはしばしば人間をだますものとしても登場してきていた。
仮にこのような自然と人間のあり方を村における暮らしの文化と呼ぶなら、この地域ごとにつくりだされた文化とともに自然と人間の多様な関係が形成されていた、といってもよいだろう。
○
ところでこの自然と人間のあいだには、ふたつの要素が介在していた。そのひとつは人間とともに暮らす動物たちである。犬は野生の動物を追い払い、人間と動物とのあいだに緩衝帯を設ける役割をはたしていた。牛や馬は農耕や輸送の仕事をしていたが、その存在が草地の維持を支え、その糞は田畑を支えていた。人間とともに暮らす動物たちが、自然と人間の多様な関係を守っていたのである。
もうひとつの要素は「信仰」である。日本には宗教とは異なる信仰がさまざまなかたちで定着している。それは山の神信仰であったり、水神信仰であったりするのだが、実際には観音信仰や阿弥陀信仰、地蔵信仰などでも地域の人たちの信仰は集めていても宗教としての形式は整っていないものがたくさくある。さらに道祖神信仰や庚申信仰なども加えれば、地域社会にはさまざまな宗教あらざる信仰が展開してきた。
それは大別すればふたつに分かれる。ひとつは里の暮らしとともにある信仰で、たとえば道祖神信仰は悪霊である道祖神を村の入り口や家の玄関の前に祀り、悪霊の強い力で入ってくる悪霊を追い払ってもらおうというものである。このような人間たちの願いを叶えてくれる神仏への信仰が地域信仰のひとつだとすれば、もうひとつは自然に絶対的真理をみいだす、すなわち自然への信仰があった。元々は山の神信仰も山岳系の山の神信仰と森林系の山の神信仰、鉱山系の山の神信仰があって、今日では里の暮らしと結んだ森林系の山の神信仰が中心になっているが、・・・だから山の神が水神となり田の神になるという里系の思想が軸におかれている・・・かつてはそれだけが山の神信仰ではなかった。たとえば山岳系の山の神信仰が聖地とするところは、山頂などの森のない岩場である。日本の自然信仰は自然に清浄なる世界をみいだす信仰で、この信仰もまた自然と人間の関係に大きな影響を与えていた。
生物同士が多様に関わり合い、自然と人間も多様に関わり合う世界は、このようなさまざまな要素をとおして形成されてきたのである。
○
生物多様性とは、人間を含めた生物の多様な関係を保証していくことである。それは間伐をすれば生物種が多様になるというような皮相的なことではない。もちろん間伐もまた必要だが、補助金だけが頼りの間伐が私たちの世界に多様な森林と人間の関係をもたらしているとは到底いえない。
むしろ大事なことは、これからの地域デザインや都市の暮らしのデザインの方である。これからの山村の地域デザインをどうつくっていくのか、そのとき森林はどういう役目を負い、森と人との多様な関係がどういう地域デザインから生みだされていくのか。さらに、これからの都市の暮らしはどうあったらよいのか。そのとき都市の暮らしと森林はどういう結びつきが必要なのか。そういう問いに答えながら、人間を含む生物が多様に関わり合う社会をつくるのが生物多様性に向けての課題である。
しかもその内容は地域ごとに異なるだろう。私の暮らす上野村で森と村人や都市の人々が多様に関わり合うかたちと、多少の雑木林が残る都市郊外の住宅地の人々が森との間に多様な関係を創造するかたちが同じであるはずはない。さらに伝統的な林業地での多様な関係と、林業技術の蓄積をもたない多くの山村の関わり合うかたちも同じものではないだろう。
ある意味では、間伐をすれば生物種が多様になると全国一律で同じことを言っていること自体が、生物多様性の思想としては貧弱なのである。そういうのであれば、全国一律の方針としてしか生物多様性の課題が語れなくなった戦後史の問題点、戦後の森林管理の問題点をも同時に議論しなければならないだろう。
今年の秋、名古屋で生物多様性条約に巻なする国際会議が開かれる。その年に森と関わってきた私たちは何を語るのか。私たちはそろそろ狭い意味での森林プロパーから脱出すべきである。
(本記事は森づくりフォーラム会報 2010年8月発行号に掲載された記事です。)
*****************************
写真:中沢 和彦(森づくりフォーラム)
*****************************
2010.08.01 森づくりフォーラム会報136号寄稿